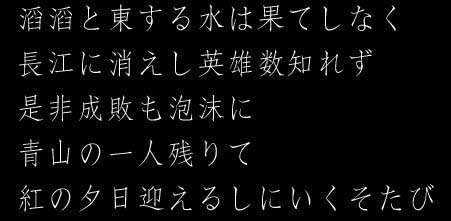 |
第一話「乱世の息吹」
written by 夏侯惇
2003.11.24(発表) 2004.6.11(修正)
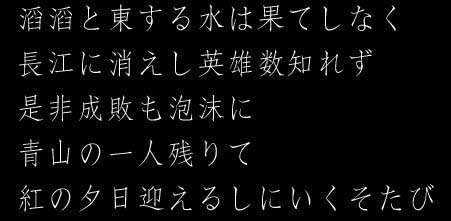 |
時は後漢の霊帝の治世。
そもそも天下と言うものは分かれれば必ず統一され、長く統一が続けば必ず分かれるもの。
すなわち周王朝が衰えて七国が分かれ争い、秦が滅んで楚漢分かれ争ったのは典型的な例で
あると言えよう。
高祖劉邦が漢王朝を興して以来、途中王莽に滅ぼされながらも約400年に長きにわたって
栄え続けてきた漢朝も、官僚の腐敗により衰えを見せ始めた。
腐敗の決定的な原因は先代の桓帝にある。
桓帝は正義の士を弾圧し、宦官を重用した。
それによって官僚の間では汚職が横行し、民は困窮していた。
今天下には飢饉が起こり、疫病が流行し、天変地異が相次いでいる。
暗愚な皇帝、我が物顔に振舞う宦官のために国の政は乱れる一方である。
そのように国が乱れれば治安も悪くなる。
それは東漢の都たる洛陽も例外ではない。
そうすると
「きゃぁ〜〜!!」
「花嫁が攫われたぞ〜!!」
こんな事件も起こってくるわけで・・・。
どうやら婚姻の儀の最中に花嫁が強奪されたらしい。
賊に攫われた若い女性がその後どういう運命をたどるかは言わずともわかるだろう。
そういう面では彼女は幸運だった。
いや、攫われたのに幸運も何も無いとは思うが、
とにかく彼女を攫った相手は普通のそこいらのごろつきではなかったということだ。
街外れの廃屋
ここに数人の男たちがいた。
男と言っても少年といっていい年齢の者達だ。
その中でその少年は窓際に佇んでいた。
中性的、いや女性的とも言うべき顔をしている。
身長は六尺八寸(161.5cm)ぐらいであろう。
その彼は目をつぶり外の物音に注意を配っていた。
「開けろ!」
その声が聞こえるや否や少年は一気に窓を開けた。
その瞬間窓から男が部屋の中に飛び込んできた。
男は受身を取って飛び込んだときの勢いを殺し、身軽に立ち上がった。
「よ、真司!ただいま」
少年に向かってにやりと笑いながらそう言う少年。
背は真司と呼ばれた少年より少しだけ高く、目が細いのが特徴だ。
「おかえり、孟徳」
真司はそう返事をする。
「あれ、本初たちは?」
そう尋ねる真司に孟徳と呼ばれた男はおどけながら答える。
「さあ?捕まらないように散り散りに逃げたからな。
ま、そのうち戻ってくるって!」
そんなこんな言っているうちに一人の男が廃屋の中に飛び込んでくる。
・・・窓ではなく入り口から。
それもそのはずその少年は真司や孟徳よりもかなり背が高く、
さらにはその脇に女を一人抱えていたのだから、窓から入れるはずが無い。
「はぁ、はぁ・・・。孟徳、なぜ私を置いて一人で逃げた・・・」
「仕方ないだろ?二人で運ぶよりも一人で運んだ方が早いし、
それなら体が大きくて力のある本初が運ぶのは当然だろ?」
「下手すりゃ捕まってたかもしれないんだぞ!?」
「捕まらなかったんだからいいじゃないか、本初。
結果がすべてさ」
「ちょっとちょっと・・・喧嘩はやめてよ、二人とも」
口喧嘩を止めようとする中性的な少年。
彼以外の少年達は「また始まったか。」という顔をするだけで一向に止めようとはしない。
さて、ここでこの少年達の紹介をしておこう。
まず、口げんかを始めた二人を止めようとしている少年。
女顔でちょっと頼りない顔をしている彼は
姓は碇、名は義、字(あざな)は真司。
汝南郡項県の出身の13歳。
父源道は高官であり、なかなかの家柄といえる。
真司は長子であり、本来ならば後継者の座は安泰ともいえるのだが、
真司の母は真司の妹で年子である麓を産んですぐに亡くなってしまい、
その後源道が後妻を娶ると次第に父や継母から疎まれるようになった。
更に継母に男子が生まれたことによって父との疎遠と継母との確執は決定的なものとなり、
家督の相続が危うくなってきている。
特に継母はなんとかして真司を家督争いから除こうとしている。
親との関係は最悪である真司だが碇家内に味方がいないわけではない。
むしろ味方の方が多いくらいだ。
妹の麓はいつでも真司の味方であるし、碇家に仕えるものや食客達の大半は真司に同情的だ。
「家督は長男が相続するのが道理である」という観点から真司の味方となるものもいた。
真司のどこか人を惹きつけてやまない不思議な魅力も味方を増やす一因となった。
学問、武芸などに関しては可もなく不可もなし。
口げんかをしている二人のうち背が高く、かなり整った精悍な顔をした少年が
姓が袁、名が紹、字が本初である。
汝南郡汝陽県の生まれの15歳で、祖父の祖父袁安から叔父の袁逢に至るまで、
四代続けて三公(宰相である司徒、軍部の最高位である大尉、
司徒の補佐である司空という権力の頂点たる3つの官職最高位のこと)を輩出した
超名門の出である。
父の袁成は司徒・大尉を歴任した袁湯の次男として生まれたが、
本初がまだ幼いうちに若くして亡くなったため、
本初は三男袁逢、末弟袁瑰の二人の叔父に目をかけられて育てられている。
学問、武芸ともに秀でたものを持っている。
口げんかをしている二人のうち背は普通で目が細い少年。
彼は姓が曹、名が操、字が孟徳である。
沛国譙(しょう:言に焦)県生まれの14歳で、前漢の功臣の子孫であり名門であるのだが、
祖父が宦官(去勢を受けた男で、皇帝や皇后のそば仕え)ということで
清流派の名士達からは快く思われていない。
勿論、祖父の曹騰は宦官なので血のつながりはなく、父の曹嵩は養子である。
曹嵩は元々夏侯氏の出なので本当の血のつながりは夏侯氏である。
父からは可愛がられているが、叔父との折り合いは悪い。
学問は飛びぬけてでき、頭の回転は本初をはるかに上回る。
武芸にも優れ、力では本初に負けるが技術で勝る。
父、母と確執のある真司。
実の父が早世した本初。
叔父と仲が悪く、宦官の孫として偏見を受ける孟徳。
そんな三人が知り合ったのは偶然であった。
その日、真司は心がもやもやとしていた。
いくら味方してくれる者が多いとはいえ、親との確執は真司の心に影を落としていた。
真司は気晴らしの為に一人馬に乗って野山を駆け回っていた。
そこで悪ガキども(とはいっても皆それなりの家柄の子なので、
悪ガキというよりもやんちゃ坊主とか放蕩息子といった方が正しいだろうか)
を引き連れて狩にやって来ていた本初と孟徳に出くわしたのである。
そして一緒に狩をしないかと誘われてそのまま意気投合し、
いつのまにか不良グループに加えられてしまった。
そして、これまたいつの間にか真司の家は彼らの溜まり場となり、
更には本初・孟徳と並ぶグループのリーダー格の一人に祭り上げられてしまったである。
真司は家柄も良かったし流されやすい性格だったので、
自然とそうなり真司自身もそれを受け入れた。
有体に言えば、何も考えてなかっただけとも言える・・・。
それ以来、真司は本初や孟徳達と一緒に勉強したり、
剣の稽古をしたり、狩に出かけたりしている。
そして暇な時は、たまに孟徳が思いつく悪戯を実行することもあった。
今回の花嫁泥棒も孟徳の思いつきだ。
別に彼らは女性に飢えているわけではなく、
言うなれば暇を持て余した子供の日常生活にはない刺激を求めての行動だ。
話を元に戻そう
永遠に続くかと思われた二人の口喧嘩だったが、真司の一言によって終わりを告げた。
「二人とも、いい加減にしないと官憲が来ちゃうよ?」
その言葉に二人ともころっと矛を収める。
「たしかにそうだな、捕まっちまうと叔父貴がうるさいしな・・・」
と孟徳が言えば、本初も、
「私も叔父上に迷惑をかけるわけにはいかないな」
「ようし、皆引き上げだ!!」
「「「「「「「「「「「「「「おう!!」」」」」」」」」」」」
孟徳のかけ声にそれまで本初と孟徳の口げんかに対して我関せずという態度をしていた
他の少年達が勢いよく返事を返す。
「ちょ、ちょっと待ってよ!」
真司が廃墟から出て行こうとする孟徳・本初達をとめる。
「あの花嫁さんはどうするのさ!」
「う〜んそうだな・・・」
少し考える本初。
そんな時孟徳が提案をする。
「真司の部下の加持にまかせりゃいいよ。
どうせ今日もついてきてそこら辺に隠れてるんだろ?なあ、加持さん」
孟徳のその言葉に無精ひげを生やした男が現れる。
「いやいや、ばれてましたか。さすがは曹孟徳様ですな」
苦笑いをする加持。
「というわけであとは加持さんに任せて退散するとしようぜ!」
孟徳の言葉に今度こそ本当に撤退を始める少年達。
「加持さん、いつもいつも申し訳ありません」
真司が加持に声をかける。
「いえいえ、私は真司様の部下ですから主君のためならこれしきのこと・・・」
だから気にすることは無い、と加持は言った。
加持は本当にそう思っていた。
孟徳のこの一言があるまでは・・・。
「そうだそうだ、真司。気にすることは無い。
部下は使うためにいるんだからな。
それに加持さんは攫われた花嫁を賊の手から奪還した英雄になれるんだから感謝してもら
ってもいいくらいさ」
この一言に加持は一気に気分を害した。
さらに
「それもそうだな。英雄になれるんだから気にすることは無いよな」
本初のこの一言で加持の堪忍袋は切れかかった。
しかし、顔を引きつらせながらもなんとかそれを耐えて加持は少年達を見送った。
真司が最後まで申し訳なさそうにしていたことは加持にとっては多少の救いとなった。
そうでなければ自分が憐れすぎる。
「あのくそがきども・・・いつかお灸を据えてやるからな!」
そう毒づいたものの加持は自分がそれを果たすことができないことがわかっていた。
「大体、何故私の主人で実行犯でもない真司様が申し訳なさそうにして、
私の主人でもない上に直接実行したあいつらが偉そうにするんだ・・・」
ぶつぶつと文句を言いながらも花嫁を花婿の元に返すという任務にかかる加持であった。
撤退した本初たちは真司の家に集まって話題に花を咲かせていた。
「それにしても、あのあっけに取られた花婿の顔、最高だったよなあ、本初。」
今日の悪戯に関する話題で盛り上がっている少年達。
「ああ、最高だったな。真司も一緒にこればよかったのに」
「僕はいいよ、あんまり気乗りしないしね」
「ほんとはあいつにばれるのが怖いだけだろ?」
意地悪く笑う孟徳。
「あ、飛鳥なんか怖くないよ!!」
「おい、真司。孟徳は飛鳥のことだなんていってないぞ?」
と本初が指摘する。
「・・・・・・」
沈黙してしまう真司。
「まあ、真司をからかうのはここまでにしようか」
「そうだな」
話は今日の悪さの話から次第に国家の話に移り始める。
「濁流(宦官や外戚、ここでは宦官のこと)が前にも増して力を握り始めたな・・・」
本初が言う。
「ああ、党錮の禁で清流派(宦官や外戚を濁流と見なして対抗した良識者たち)が軒並み
駆逐されたのが痛いな」
と孟徳。
「去年は竇武大将軍・陳大傅が宦官に殺されたし、
今年は宦官に対抗する清流派が100人くらい投獄されたし、
僕の親戚も危なかったらしいよ」
これは真司。
「知ってるか?今年玉座の間に大蛇が出たらしいぞ」
「本当か、孟徳」
「ああ、きっとこれは何かの前兆だろう」
「そうか、まあいずれにせよ国は乱れるな・・・」
「国が乱れる・・・か。できれば一生平穏に暮らしたいんだけどなあ・・・」
「真司、もはや国の乱れはかなりひどくなってきている。大異変が起こるのも時間の問題さ」
「そのとおりだ。真司、覚悟を決めておくんだな」
「うん・・・」
真司も馬鹿ではない、自分の事なかれ主義が今の時代にはあっていないことは分かっていた。
(でも、嫌だなあ・・・。喧嘩なんかしないで皆仲良くできればいいのに・・・)
我ながら馬鹿なことを考えているとは真司も思っていた。
『このような自分の考えを幼馴染の少女に知られたら彼女はどういうだろうか?』
そう思ってすぐに真司は自虐的な笑みを浮かべる。
彼の頭の中には『アンタは甘すぎんのよ!』と飛鳥が言う姿が鮮明に浮かんでいた。
その男は茫然と立ち尽くしていた。
官吏登用試験に落第したからである。
彼、張角は賢い男だった。
地元でも有名な秀才で、彼自身自分の才能を自覚し、
自分が並外れた人物であると微塵も疑っていなかった。
勿論、才能に溺れる事無く努力もしてきた。
そして腐敗した王朝を自分が改革して内側から立て直し、天下万民を安んじるのだ。
自分にはそれができるはずだと信じていた。
官吏登用試験は張角にとってその第一歩でしかないはずだった。
しかし、結果は落第。
「なぜだ・・・なぜこの私が落第しなければならんのだ・・・。
私には才能があるはずだ、努力も怠らなかった・・・。
それとも私には才能が無かったと言うのか?」
呟く張角に答えるものはいなかった。
その時、張角の頭に直接響いてくる声があった。
それは張角の中のもう一つの人格だったのかもしれない。
その声は張角に言う。
「違う、お前には才能があった」
「努力も怠ることは無かった」
「悪いのはお前じゃない、お前の能力が足りなかったわけじゃない」
「そう、悪いのはお前の能力を認めようとしないこの国の連中だ」
「見てみろ今の世の中を。宦官や媚びへつらうことだけがとりえのような無能な奴がこの国
を動かしている。まともな奴もいるがそんな者たちは迫害される」
「悪いのはお前じゃないんだ」
その声を聞き、張角は茫然とした状態から立ち直った。
「そうだ、私は悪くないんだ・・・。私を認めないこの世の中が悪いのだ。
見ていろ!私を認めようとしなかった者達よ!今に見返してやるぞ!」
そこには理想に燃える秀才の姿はなかった。
そこにいるのは狂気と野心を抱えた復讐の鬼だった。
時は建寧2年(169)、天下は今まさに激動の時代を迎えようとしていた・・・。
|
作者の夏侯惇様に感想メールをどうぞ メールはこちらへ |
<アスカ>夏侯惇様がついに動き出したわっ!
<某管理人>長い間寝てはったんですか?
<アスカ>アホ管理人っ!一大プロジェクトが始まるのよ。
<某管理人>一大プロジェクト?
<アスカ>そうよ!いよいよ、三国志が始まるんじゃない!
<某管理人>おっと、あの三国志でっか。
<アスカ>あのって、他にあるわけないじゃない。それでその気合の入った作品をここに投稿していただけるのよ!
<某管理人>わっ!おおきに、ありがとさんです。
<アスカ>このあとどうなってくんでしょうね。楽しみっ!
<某管理人>わても楽しみです。がんばってなっ!
さぁて、夏侯惇様3作目。
ついに三国志の世界が登場!
但し、気をつけてよね。
三国志でエヴァを描くんじゃなくて、
エヴァキャラを使って三国志にアプローチするんだからね!
でも、いきなり幼馴染の二人で、アリガトね!
夏侯惇様、素晴らしい作品をありがとうございました!