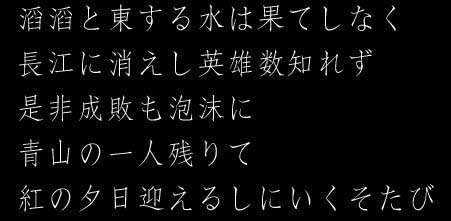 |
第二話「冬月先生」
written by 夏侯惇
2004.7.11(発表)
★クリックすると紹介ページが開きます
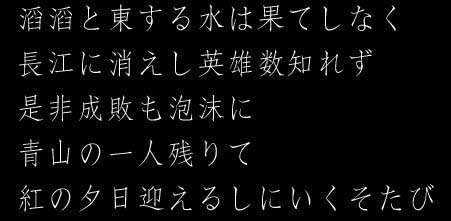 |
さて何度も言うが今は後に言う後漢朝、霊帝の治世である。
前回官の腐敗によって世が乱れ始めたと申し上げたが、少し詳しく説明しよう。
光武帝が後漢朝を立ててよりすでに約200年が経った。
この頃になると皇帝の権力は衰え、
次第に皇帝の母方の親戚である外戚が権力を持ち始めた。
外戚は自分の娘または妹が皇帝の妻となって男児を産み、
それが皇帝になる事によって皇帝の祖父あるいは伯父として権力を振るう。
幼い頃はいいなりになっている皇帝も、成長して自分の立場が分かってくると
「なぜ朕は皇帝なのに全く権力がないのだろうか?」と思うようになってくる。
そこで登場するのが宦官である。
待遇に不満を持ち始めた皇帝は側仕えである宦官に相談する。
宦官は皇帝の寵愛を受けて権力を握り外戚と権力争いをはじめる。
こうして宮廷内では宦官と外戚が血で血を洗う抗争を行っていた。
そして、宦官と外戚以外にもう一つ、第三の勢力がある。
それが清流派と呼ばれる高級官僚勢力だ。
彼らは宦官や外戚などを「濁流」とみなし、自分達を「清流」とみなした。
本初の袁家などはその代表格と言える。
また、真司もこの勢力に属している。
孟徳も一応この勢力と言えるのだが、曹操の父は宦官の養子なので非常に微妙な立場だ。
さて、宦官や外戚は自分勝手な政治を行い、国家を混乱に陥れた。
これによって「清流派」はますます宦官や外戚―特に宦官―に対する憎悪、
嫌悪の情を強くしていったのである。
真司達が出かけている頃、碇家に一人の少女がやってきた。
その少女は遠慮なくずかずかと屋敷の中に乗り込むと、真司の部屋へと向かう。
「真司〜!今日もどっか遊びに行くわよ〜」
「飛鳥様、真司様はご病気でして誰ともお会いにならないということで・・・」
家の者がそう言って止めようとするが飛鳥の耳には聞こえない。
なぜならその召使は飛鳥の遠くから恐る恐ると言った感じで話しかけているため、
飛鳥まで声が届いていないのだ。
飛鳥は武芸百般に秀でており、自分の邪魔をするものには容赦しない。
下手に機嫌を損ねるとどうなるかわからない。
そのため碇家の召使達は遠巻きに制止を呼びかけるだけで、近づこうとしない。
そんなこんなしているうちに飛鳥は真司の部屋へとたどり着いてしまった。
「バカ真司!」
「アタシが来たって言うのに出迎えもしないなんてどういう了見なの!
・・・って、あれ?」
飛鳥の視界に映ったのは空っぽの部屋。
きょろきょろと部屋を見渡した飛鳥は、近くにいた召使に声をかける。
「ちょっと、そこのアンタ!」
「は、はい!わ、私でしょうか?」
あからさまに怯える召使。
「バカ真司はどこへ行ったの?」
「し、真司様なら袁本初様、曹孟徳様たちとおでかけになりました・・・」
「ぬぁんですってぇ〜!?アタシを置いて遊びに出かけたって言うの?」
「ひいっ!お許しを!!」
飛鳥のあまりの剣幕に思わず謝ってしまう召使。
彼女にはなんの責任も無いと言うのに哀れである。
「バカ真司の分際でアタシになんの断りもなしにでかけるなんて、
良い度胸じゃない!!」
この落とし前をどうやってつけさせようかと考えながら、
飛鳥は碇家の屋敷をでていく。
後には、放心したように座り込む召使だけが残された。
翌日。
「こぉら、馬鹿真司!起きなさい!」
真司の安眠は少女の怒声によって終止符を打たれた。
「なんだ・・・飛鳥か」
「今日は先生のとこに教わりに行く日でしょうが!
だからわざわざ迎えに来てあげたっていうのに、何よその態度は!」
(うわあ・・・なんだか今日の飛鳥機嫌悪いな・・・)
いつもならこのぐらいでは怒らないのに・・・と思う真司。
「ご、ごめん・・・」
昨日の事により飛鳥の機嫌は最悪である。
いや、むしろ昨日よりもさらに機嫌が悪化しているかもしれない・・・。
「・・・アンタ、アタシに黙ってどこ行ってたのよ?」
元々気が長い性格でもない飛鳥、いきなり本題を切り出す。
「え?」
「アタシに黙って昨日どこ行ってたのかって聞いてんのよ・・・」
ゆっくりとどすの聞いた声で話す飛鳥。
ある意味怒鳴られるのより怖い、と真司は思った。
(うわぁ・・・飛鳥の目、すわっちゃってるよ。
どうしよう、なんて言えば許してもらえるかなあ)
「ご、ごめん・・・」
とりあえずまた謝ってしまう。
「アンタねえ、なんでも謝ればすむと思ってんの?
アタシは昨日どこ行ってたのって聞いたんだから、
それに答えなさいよ!」
「も、孟徳と本初と一緒に狩に行ってたんだ」
なんとか言い訳を考える真司。
花嫁を攫ってましたなどといえるはずがない。
「ふ〜ん、狩ならアタシも誘ってくれれば良かったのに」
ジト目で見る飛鳥。
「い、いや、いつも飛鳥も一緒に行ってるからさ、
た、たまには男だけで行こうって本初達と約束してたんだよ」
「ふ〜ん、あくまでもしらを切ろうって言うのね!」
「し、しらを切るも何も、ほ、本当の事だよ・・・」
「馬鹿真司のくせに嘘をつくなんていい度胸ね。
アタシ知ってるのよ!アンタ達が人攫いの真似事してたってことを!」
「え・・・ええ!?な、なんで飛鳥がその事を!?」
「ふん、美郷のやつに聞いたのよ!」
美郷とは飛鳥の御付の者の一人であり、酒豪として有名な女性である。
その美郷がなぜ真司達の所業を知り得たか。
それは真司の護衛である加持が彼女の夫であり、
夫の加持に愚痴を聞かされたからだ。
そして、真司達の悪行を知った美郷は面白半分にその事を飛鳥へ注進に及んだという次第である。
(か、加持さん、恨みますよ!)
真司は美郷が知っていたという事実から、
加持から情報が漏れたことを把握した。
がしかし、加持への報復を考える前に真司には
飛鳥の機嫌をどうおさめるかという難題が立ちはだかっていた。
(すみません、真司様。
俺も愚痴を言わないとやってられなかったんです!)
柱の影から覗いていた加持は心の中でそう詫びた。
数刻後、飛鳥の機嫌は何とか直っていた。
その代わり飛鳥と並んで歩く真司の両頬は真っ赤に腫れ上がっているが、
このくらいで済んでよかったというべきだろう。
並んで歩いていた二人はやがて一つの邸についた。
ここが、二人の学問の師の住んでいるところである。
「「冬月せんせ〜!」」
二人の声を聞いて邸から一人の男が顔を出した。
「おお、真司君に飛鳥君、よく来たね」
この男が冬月である。
冬月というのは道号であり本当の名前は別にあるはずなのだが、
皆が冬月と呼ぶため本名を使われる事はほとんどない。
冬月は現在38の齢を数える。
兵法、儒学などあらゆる学問に通じ、元は漢朝に仕えていたのだが、
あまりの腐敗ぶりに嫌気がさして野に下った。
そして現在は世の名士、賢者と呼ばれる人物と交流を持ったり、
学問を教えたりしながらすごしていた。
自分のことを「博覧強記」「文武両道」
と自称する飛鳥でさえも舌を巻くほどの知識の持ち主だ。
もっとも、飛鳥の師は冬月であるのだから当然なのだが。
さて、冬月の邸には真司達以外にもたくさんの弟子達が集まっていた。
「先生、今日は何を教えていただけるのですか?」
弟子達の誰かが尋ねる。
「ふむ、今日は兵法を教えよう」
「やったぁ!」
喜ぶ飛鳥。
「兵法か・・・」
対照的に気乗りしない様子の真司。
それを見て冬月が呟く。
「そういえば、真司君は兵法は覚えが悪かったな」
「まったく、馬鹿真司は情けないわねぇ・・・」
飛鳥が真司を馬鹿にしたように言う。
まあ、本当に馬鹿にしてる訳ではなく、
真司に奮起して欲しいがゆえにわざとそういう言い方をしている訳だが。
「だって、兵法って戦争の仕方でしょ?
僕、人を殺したりするの嫌だし、戦争は嫌いだよ」
「アンタ馬鹿ぁ?なに甘っちょろいこと言ってんのよ!」
「まあまあ、飛鳥君。真司君の言っている事も間違ってはいない。
かの大軍師孫武も『百戦百勝は善の善なる者にあらざるなり。
戦わずして人の兵を屈するは、善の善なる者なり。』
と言っているように戦をせずに敵を降せるのならばそれが何よりなのだよ」
「は、はぁ・・・」
真司を怒鳴りつけた飛鳥であったが、冬月に諭されて意気消沈してしまう。
「しかし、だからと言って兵法を勉強したくないと言うのは感心しないね。
兵法はただの戦争のためのものではない、
その中には著者の人生観や処世術が詰め込まれている。
人生を生き抜くための知恵を得るために勉強する
と思って兵法を学んでみてはどうかね?
今まさに時は乱世を迎えようとしているだからなおさらだよ」
「なるほど、これからは兵法もがんばる事にします!」
真司、本初と別れて家路に着いた孟徳だったが、
邸の直前で叔父が出てくるのが見えた。
(あちゃあ、嫌な奴にあったな・・・)
孟徳はもっぱら不良仲間と遊んだり悪さをしたりしていたのだが、
其の度に叔父が孟徳の父である曹嵩に告げ口をする。
孟徳に会う度に説教をしてくる事もあいまって
孟徳にとって叔父は非常に厄介な相手だった。
(さて、どうしてものか・・・)
ここで孟徳は一計を案じた。
叔父が近づいてくると孟徳は顔をゆがめ、ひくつかせる。
「どうした、孟徳。なにかあったのかね?」
「いえ、急に顔がしびれて・・・」
「なんと、それは大変だ。何かの病かもしれない」
驚いた叔父は急いで曹嵩に報告しに行く。
孟徳はそれを見ながらにやりと笑うと、自分の部屋へと帰っていった。
さて、叔父の報告に驚いた父は早速孟徳を呼びつけた。
しかし、孟徳の顔はなんともなっていない。
「操よ、顔がしびれているそうだがもう大丈夫なのか?」
「はて?なんのことでしょうか?
私は顔なんかしびれておりませんよ」
「しかし、弟の話ではお前の顔がしびれているという事だったのだが・・・」
「それは叔父さんのでたらめですよ、
叔父さんには嫌われていますからね。
そういうありもしない事をおっしゃったのでしょう」
「う〜む・・・」
曹嵩は孟徳の事を子供の中で最も可愛がっていた。
そのために、これ以降叔父の言うことを信じなくなってしまい、
孟徳は気兼ねせずに遊べるようになった。
本初が邸に帰り着いた時、一人の男が迎えに出てきた。
「本初、今帰ったか」
それは本初の叔父袁逢であった。
「これは叔父上、ただいま帰って参りました」
門の外まで出てきた叔父に多少驚いたものの、
本初は丁寧に挨拶を返した。
「うむ」
「はて、叔父上。難しい顔をなさっていかがなされましたか?」
「本初よ、お前は将来袁家を背負って立つ男だ。
あまり問題を起こしてくれるなよ?」
目配せをしながら言う叔父に、
本初は孟徳たちとの所業が知られている事を悟った。
「わかりました、充分に身を慎みましょう」
「うむ、お前は文開兄上の唯一のただ一人の子息なのだからな」
「はい、わかりました」
袁逢はそれ以上何も言わず、自分の邸へと戻って行った。
「まさか、叔父上に伝わっておるとはな」
そう呟くと本初も自分の邸へと帰ろうとする
(袁家などの豪族といえるような者は、
邸が一族同士集中しているのが普通である)
「おやおや、兄上。今お帰りですか?」
「なんだ、公路か」
声をかけてきた少年は本初の従弟の公路
(姓が袁、名が術、字が公路)であった。
なぜ「従弟」の袁術が本初の事を兄上と呼ぶのか、
それは同族(同姓)の従兄弟は兄弟に準ずる扱いとなるためだ。
平たく言えば兄弟同然ということだ。
閑話休題
「ふん、兄上はいいですねえ、父上や叔父上に目をかけられて。
いや、えこひいきといったほうがいいかな」
「別に贔屓になどされてない」
「そう思ってるのは本人だけなんじゃないの?」
「・・・・・・」
「確かに兄さんは御祖父様の次男の文開伯父上の長子で、
僕は三男の子だけど・・・」
「だけど、今の袁家の当主は誰がなんと言おうと僕の父さんだ、
その息子の僕が継いだっていいじゃないか!
それなのに、父上も叔父上も皆『本初、本初』って
兄さんばっかり優遇されて・・・」
「・・・・・・」
「僕は納得してないからね!僕は絶対に兄さんに袁家を継がせないよ!
大体、兄さんの母親は妾じゃないか!
そんな奴に袁家を継がせるなんて認められない!」
言いたいことを言うと、公路は一つ大きく息をした。
そして本初に背を向けて朝靄に霞む門をくぐり、
父袁逢と同じ方向へ歩いていった。
「やれやれ・・・」
呆れた様な声をだすと本初もまた自分の邸へと帰っていくのであった。
冀州は鉅鹿郡。
官吏登用試験に漏れた張角は故郷に帰ってきていた。
漢朝への復讐を誓ったものの、
単家(庶民)である張角にそれを成し得る力があろうはずもない。
そのため張角は古今東西の書物を捜し求め、
読み漁って方策を練り、雌伏の時を過ごしていた。
そんなある日、張角はある本と出会った。
「太平要術・・・?」
それは妖術や仙術といった類の物に関する書物であった。
「ふん、くだらん」
張角は現実主義者である。
妖術の類などは信用していない。
張角はその本に目もくれずに捨てようとしたが、
ふとある考えが頭に浮かんだ。
世が乱れると民は心のよりどころを求める。
そのため世が乱れるたびに新興宗教が生まれ、
民の心のよりどころとなった。
王朝の転覆を図る張角にとって民心を掌握して扇動することは必須であった。
そうだ、これを利用して道教の教祖になればいい。
張角の一世一代の謀が動き始めた。
|
作者の夏侯惇様に感想メールをどうぞ メールはこちらへ |
さぁて、夏侯惇様3作目「Fellows」の第2話よ。
ついにアスカ…じゃない、飛鳥が登場!
まったくもう馬鹿シンジのヤツ、いつの時代でも
私に隠れてこそこそこそ。
その根性を叩きなおしてやるっ!
人物紹介のページもできたから活用してよね。
夏侯惇様、素晴らしい作品をありがとうございました!